前回に引続きサブサンプションアーキテクチャについて話します。
サブサンプションアーキテクチャの特徴は、レベル1、レベル2といったいくつものシステムを積み上げていくことができるということです。しかし単に重ねればうまくいくというものではないのです。問題は、システムどうしの接点をどうするかということです。積み上げが7、8つならば何とかなるのですが、何十何百となると無理です。
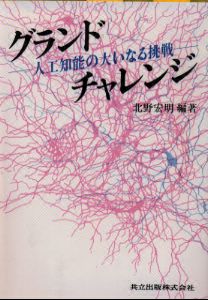 この本は人工知能の未来の可能性と方向性を探った本です。サブサンプションの問題をどのように解決するかといった方法をいくつか取り上げています。
この本は人工知能の未来の可能性と方向性を探った本です。サブサンプションの問題をどのように解決するかといった方法をいくつか取り上げています。
ALN(Adaptive Logic Network)という方法は、ニューラルネットワークを利用しています。いわゆるニューロコンピューターの仕掛けです。脳細胞に相当する素子からなるネットワークを作り、それに課題を与えて、ためしに解を出させる。その解が満足のいかないものだったらもう一度トライさせる。これを繰り返してうまい解を出してくる回路を見つける、という方法です。
それから、GA(遺伝アルゴリズム)を使った方法もあります。生命が進化の過程でさまざまな能力を獲得してきたように、コンピューターに何度もトライさせて良いものを残させるのです。本質的にはALNにかなり似ています。
もう一つは、コンピューター自身に学習させる方法です。動物に芸を教える時に、うまくいったら御褒美を与えるというやり方は強化学習といいますが、これと同じようなことをコンピューターに対してやるのです。コンピューターに課題を与えて、うまくいったら何らかの報酬を与えるのです。
以上のような方法を利用して、サブサンプション積み上げ問題の解を求めさせようというのです。
人体というのはSSA(サブサンプションアーキテクチャ)の膨大な積み上げからなっています。積み上げの問題は進化が解決してきたのです。同じように、自然が進化を通して獲得してきたことを利用しようというのです。生命の歴史の中で起こったことを見てみると、生命は、SSAのような大きなシステムを作った時に、中央集権的CPUが存在するシステムではなく、ラングトンの生命の定義にあったように、自分の近傍とだけのローカルなやりとりで全体がうまくいくようなシステムを獲得してきたのです。
西欧では、神というものがいて自然界は合目的的に作られたと伝統的に思われてきました。しかし、歴史の進行とともに、どうもそうではないということがわかってきました。自然そのものの見方が変わってきました。自然界は、全体が自律的に生きているのです。多くのエレメントがローカルな入出力で大きな生きた生命体を創発的に作り出しています。これはSSAの例からなるほどと思えます。
人によっては進化のプロセスが合目的に進行してきたと考える人が結構います。この進化は…のために起きたんだ、といういい方をする人です。しかし、現実には、進化は…のために起きたのではないのです。都合のいいのがたまたま残っただけなのです。生き残ったものがその形質を活かして生活しているだけなのです。

下山研の6本足ロボットは、1本1本の足が独自の系からできています。そして、その歩行は合理的な3足歩行が基本になっています。ではどのように3足歩行をしているかというと、1本の足が、自分が上がる時は直近の足には上がるなという信号を出すのです。この命令は、直近の足にしか出していないということがポイントです。このようなローカルな情報のやりとりで動いているのです。
下山研の6足歩行ロボットが歩いているのをこの前映像で示しました。あのなかで、薄い板が2,3枚積み重なった障害物を必死に乗り越えている場面がありましたね。あの処理を中央集権的なシステムでやろうとすると、計算機の部分が大きくなり過ぎて自律的なものにすることはできません。あのロボットは、各々の足が動くうちに環境の側から、動きの結果起きたことをフィードバックで受けて自ら乗り越える方法を発見していっているのです。
自然界のシステムもこの方法なのです。神様のような中央集権的装置が命令を下すのではなく、各々が環境からフィードバックを受けてアクティブに動き、さらにフィードバックを受けて、アクティブに…と、いってみればもがくうちに解を見つけていくのです。このようなナチュラルな仕掛けは自然の中にたくさんみられます。ここで大切なのは、アクティブに動くということです。アクティブな部分がなくてパッシブな情報だけだと何も事が進行しないということがいろいろな形でわかってきました。

|
| ゴンドラネコと自由移動ネコ |
文責:勝木健雄
価値体系
人間はマイナスのレベルを自分で設定して、自分の命をかえりみない行動をしたり、自分を犠牲にしたりする。人間にはそれが正しいか正しくないかは別として、レベル0や1の自分の命を守ることよりも大切なものがあるといった価値体系をつくって行動する人もいる。これは歴史的には祖国愛とか宗教信仰によくみられてきた。
「価値体系」は数学的に「評価関数」と言い換えられる。二十代にまずなすべきことといったら「独自の美学をもつ」ことだ。これは言い換えれば「独自の価値体系をもつ」こと、「独自の評価関数をもつ」ことだ。
人間の基本的な行動、つまりレベル0や1は遺伝子に埋め込まれているといわれてるが「遺伝子のこの部分がそうだ」という正確な証明はなされてない。ただ、脳のある部分を破壊すると基本的な行動が十分にできなくなったりする。基本的な脳のシステムをつくっているのは遺伝子だから「遺伝子に埋め込まれている」といえる。人間と生物一般なんて基本的な価値体系はさほど違わないが、人間特有の行動がみられるのは人間が価値体系を自ら評価できるからだ。生物の行動は遺伝子にコントロールされるものだが、人間は遺伝子のコントロールを抜け出し、自分を build up できる。
価値体系を評価できるというのは非常に重要なことで、これができればきちんとした価値体系をつくりあげ、自分の生き方をきめていける。
脳は古い脳に新しい脳が積み重なって進化してきた。脳は簡単にいうと内側から、大脳基底核、辺縁系、大脳皮質という構造になっている。これらはそれぞれ反射脳、情動脳、理性脳と呼ばれたり、爬虫類脳、哺乳類脳、真哺乳類脳と呼ばれたりする。
よく「脳細胞140億」と言われる。しかしこれは脳の外側の大脳皮質の部分だけのことで、他の部分は含まれていない。脳には小脳という部分があってそこだけでも脳細胞は1000億あるって言われてる。脳全体ではなんと数千億になるっていわれてる。また、脳には「白質」の部分と「灰白質」の部分があって、前者は文字通り白くて、後者はよくいわれるところの脳みそだ。これはどちらも神経繊維でできていて、コンピューターでたとえるなら、前者はチップとチップをつなぐワイヤーで、後者はチップだ。また、灰白質(つまり脳みそ)の4分の3は辺縁系と大脳基底核にあるといわれてる。人間の基本的行動は大脳皮質がやっているということになっているが、本当にそうなのであろうか?これはまだ解明されていない大きな疑問だ。ヒト化の歴史、つまりホニュウ類よりもっと脳細胞が増えていく歴史は大脳化の歴史だといえる。大脳化は進化の過程のあとのほうでおこる。
ハチュウ類脳よりさらに下部に「脊髄(せきずい)」というのがある。一般のひとはよく脳と脊髄を分けて考えてしまうが、どちらも発生的にも構造的にも同じだ。脳の階層構造の根本に脳幹というものがある。脳幹は植物状態や脳死の問題の時にでてくるが、やはりどちらの状態になっても人間の心臓は動いているという意味では死んではいない。レベル0はすごくしぶとくて強いものだ。外側の皮質の部分は割とすぐに眠り込んでしまうが。人間は凍死しそうになると眠くなるが、それは皮質がすぐに眠ってしまうからだ。人間が眠り込むと皮質はすぐ意識を失う。しかし寝ていても生命をささえているのはもっと内側にあるレベル0の部分だ。人間は脳を外側から順に取り去っても生きていられるから、脳の構造はサブサンプションアーキテクチャと言える。
文責:村松暁
生態系の進化哺乳類の先祖は、爬虫類である故、人の頭や脳の構造を考えるには、爬虫類に戻って考えなければならない。そこで、爬虫類から哺乳類に進化した大きな違いについて考えようとおもう。
- 冷血(爬虫類)から温血動物(哺乳類)へ
生命体は−−特に脳は−−化学反応系である。つまり温度によって反応が左右されやすい。例えば、我々が凍死する寸前に眠くなるのは、冷血になるためである。そこで脳は、視床下部によって定温を保つ。また、このための熱源は二つある。一つ目は「食物」(我々は、極端な雑食動物であるため、これだけ著しく発達した。なぜなら、食性によって生体系の範囲が広まるからである。)であり、そして二つ目は、「呼吸」だ。そもそも我々動物は、酸素を体内に取り込むことによって、化学反応をおこしており、その反応によって熱を作り出しているのである。
- 聴覚(視覚に関していえば、生物の歴史は、視覚の歴史といわれている。)
人は、三つの耳小骨を持っている。そして、これらは独特の構造をしてるため、音を対数変換する役割がある。つまり、鼓膜が強く振動したとしても、センサーはそれほど震えないのである。要するに、それらは聞こえる範囲を増やしてるのである。しかし、爬虫類のセンサーは、比較的硬いため、小さい音が聞こえないのである。
- 猿から人へ
皆さんも御周知のように、猿と人の違いは四つある。「火の使用」「道具の使用」「直立歩行」「言葉の使用」である。これら四つの条件は、脳の発達の証ともいえるだろう。
ここでは、言葉の使用について考えようと思う。言葉には、大きく分けて音声と文字がある。音声に関していえば、相当の数の動物が警戒音として使っているが、それはあまりにもシンプルなものである。そんな中で、人が音声を使い他人と意思疎通することができるのは、優れた発音器官を持っているためである。
しかし、言語に関して優れた脳を持っているのは、必ずしも我々「人間」だけではない。「猿」もまた、言語に関して優れた脳を持っているのである。その証拠に、彼らは手話をすることもできるし、キーボードをたたくこともできる。ということは人と猿との違いは、高度な言語によって意思疎通できるかどうかということである。
では、いつ頃から 人は言葉を喋るようになったのだろうか。たしかに、火や道具を使用し始めたのは、僅かながらでも痕跡が残っている。しかし、「言葉」はどうだろうか。恐らくわかる人はいないだろうと思う。なぜなら、かの有名な国際言語学の学会でさえ「人がいつ言葉を喋りだしたかということを論じる奴は学者ではない!」といわれたぐらいだからだ。それくらい言葉の起源を解明するということは困難なことであるのだ。 - 脳神経外科の歴史
新石器時代の遺跡を調査すると、三角形の形をした黒曜土の石器が大量に出てくる。これらは、脳の手術に使われたといわれている。しかし、ある時期の遺跡を境にそれらは全く出てこなくなった。それは、教会が、出血を拒否したからだ。その後、修道院が外科を始めたが、ローマ法王の命令で、下賎がするようになり、そのうち床屋がやりだすようになった。
文責:塩飽哲生
脳の基礎知識
情動
哺乳類脳といわれている大脳辺縁系が受け持つ、人間にも動物にも共通の、個体及び種族維持に関する感情体験と身体反応のことである。
- 1次性情動
- 生得的欲求で、本能にからみ、生命の維持に不可欠な欲求である。
例....飢餓、睡眠、疲労、性欲等 - 2次性情動
- 1次性情動が満たされない時、または満たされない時に感じる感情等のこと。
例....怒り、恐怖、喜び、安心感等
扁桃体
大脳辺縁系に存在し、あらゆる感覚連合野からの情報が流れ込み、その情報に生物的な価値評価を素早く与える。つまり、生物におけるサブサンプションアーキテクチャで、レベル0、1の価値体系をになっているのである。ためしに、猿の扁桃体を破壊すると、食物であるかそうでないかの判断ができなくなってしまう。例えば、普通の猿なら本能的に恐怖心を抱くヘビを見ても、逃げるどころか逆にヘビを頭からかじるという危険な行為をしたり、明らかに食べられないものを口に持っていったりする。また、ネコの扁桃体を破壊した実験では、性欲が亢進し、ネコ以外の動物とも交尾しようとしたということである。また、情動と密接な関係を持つので、感情を伴う知のメカニズムともいえる。
人間と他の動物の脳の違い
人間の脳の大きな特徴の1つは、他の動物に比べて大脳化が進み、感覚の連合野が非常に発達しているということであり、逆にいえば、ヘビ等と異なり古皮質、旧皮質の占める割合が非常に小さいということである。また、脳に刺激を与え、その時にどのような反応が起きるかを調べることによって脳の機能MAPを作ると、猿や猫等は手(指)の神経に脳の大きな範囲を使っているのに対し、人間は、手(指)、口(唇)の神経に脳の大きな部分を使っていることがわかる。つまり、人間は他の動物に比べ手と発声能力が発達しているということである。
参考文献
「三つの脳の強化」……ポール・D・マクリーン
「脳の機能と行動」……ペンフィールド
「脳を究める」…………立花 隆
文責:片岡公一
御意見・御感想をお待ちしています
ctakasi@komaba.ecc.u-tokyo.ac.jp